今年の6年生は、総合的な学習の時間に
身近な環境問題をテーマに学習を進めています。
今回は志戸川の調査をしました。
調査は、川の流れや環境、周辺の生き物などについて、
10項目ありました。
どの項目も自分がその様子を見て判断していくのですが、
子どもたちのまなざしは真剣でした。


水の透明度について調査するとき、
「先生、どういうのが透明なんですか?」
と言うので、
「底が見えたら透明って言えるんじゃないかな」
と答えると、
どこかから長い枝を見つけてきて、
川の底の方をつついていました。

そして近くで見ていた子が言うことには、
「藻みたいなこけみたいなのがいっぱいある・・・」
だそうです。
これは果たして「きれい」なのか「きれいではない」のか。
あとで教室に帰って聞いてみると、
「藻みたいなものがあって、ぼくはきれいとは思えないから、
志戸川に入って遊びたいとは思えなかった」
という感想がありました。
反対に、
「藻があるのも自然の一つだと思った」
という考えもありました。
調査は川の水だけでなく、周辺の植物や生き物にも行われました。



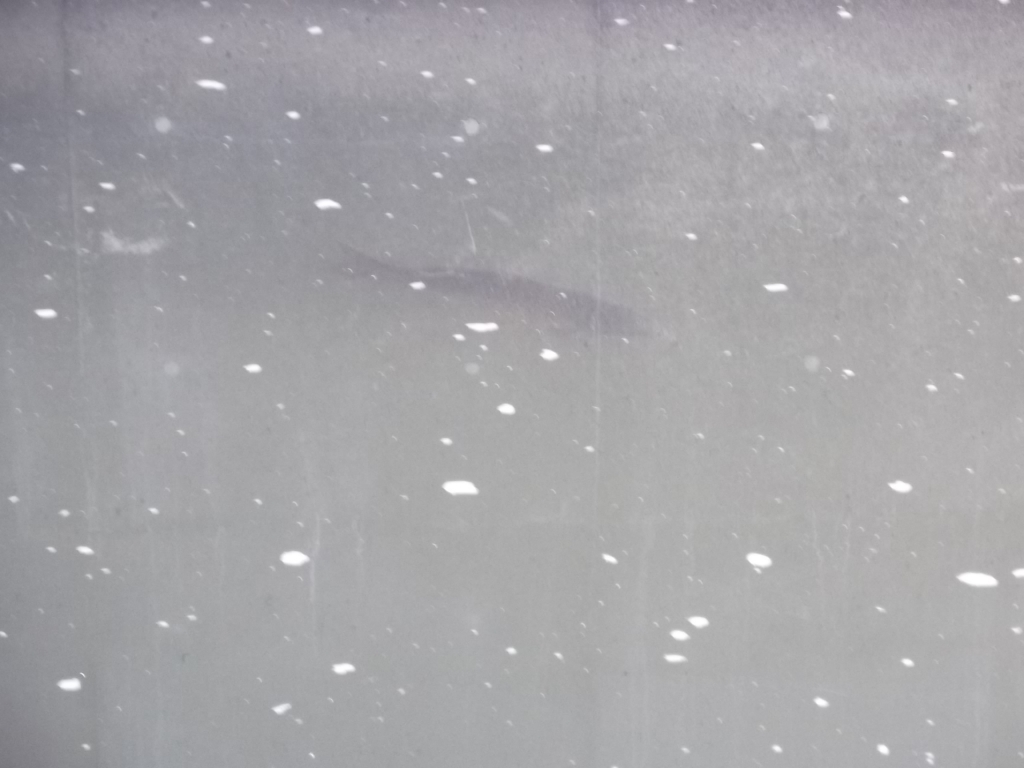
名前のわからない植物もありましたが、
とにかくたくさん植物があることはわかりました。
子どもたちは志戸川の緑のよさをよく知っていて、
「春は菜の花、秋は彼岸花がきれいだよね」
と言っていました。
調査項目に
「食べられる植物や生き物はあるか」
という項目もありました。
子どもたちは、食べられるものがあるかどうか、
よく目をこらしていました。
そんな中、
「へびいちこって食べられる?」
「いやいや、だめだと思うよ。たぶんまずいよ。」
という会話も・・・
よもぎのにおいがわからないというので、
ちょっとだけ摘んで、においをかいでみました。
においがすると言う子と、わからないと言う子。
わからないという子の方がちょっと多かったようです。
写真ではあまりよく見えませんが、
志戸川には鯉もいました。
ちょうど落合橋の下あたりにいて、
見つけたときにはちょっとした騒ぎでした。
次回は川以外のところで、
植物や生き物などの調査を行いたいと思います。
